2025.05.12
医療の知恵
骨髄検査について
みなさん、血液細胞がどこで作られているかご存知でしょうか?
血液は、骨の中にある「骨髄(こつずい)」というスポンジ状の組織で作られています。
この骨髄には「造血幹細胞」という大切な細胞があり、そこから白血球、赤血球、血小板が毎日生み出されています。血液の病気が疑われるときには、この血液工場である骨髄を検査して、詳しく診断をつけることがあります。
患者さんに骨髄検査についてご説明すると、「骨の病気なんですか?」と尋ねられることがありますが、そうではありません。
骨髄検査は骨ではなく、骨の中にある骨髄を調べる検査です。
骨髄検査には、次の2種類があります。
• 骨髄穿刺(こつずいせんし):骨髄液を採取し、顕微鏡検査、染色体検査、遺伝子検査、フローサイトメトリー(細胞表面抗原検査)を行います。
• 骨髄生検(こつずいせいけん):骨髄組織そのものを取り出して、病理検査を行います。
通常、骨髄穿刺は骨盤の「腸骨(ちょうこつ)」という部分で行いますが、場合によっては胸の真ん中にある「胸骨(きょうこつ)」で行うこともあります。
骨髄生検は腸骨のみで行います。
検査の際は局所麻酔を使用し、できる限り痛みが少ないように配慮しますが、骨髄液を吸引する瞬間に、数秒間強い痛みを感じることがあります。
そのため、「3、2、1」と声かけを行い、「1」のタイミングで息を止めることで、痛みを少し和らげる工夫をしています。
このように骨髄検査は、痛みを伴う可能性があるため、血液検査だけでは診断がつかない場合に限り実施しています。
たとえば、鉄欠乏性貧血やビタミン不足による貧血、血球減少などでは、骨髄検査を行わず診断・治療することもあります。
血液内科 副部長 板垣 充弘
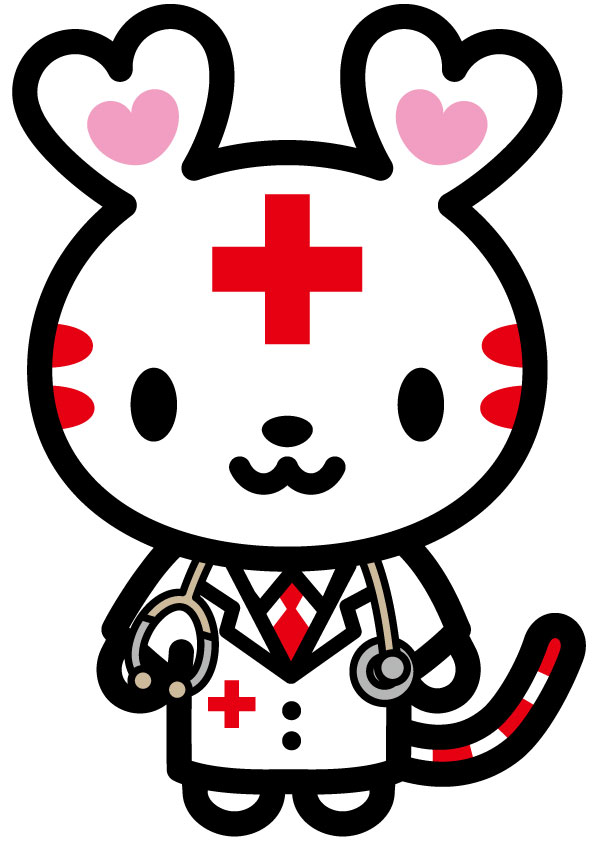

 082-504-7576
082-504-7576